
「世界一受けたい授業」減量外来ドクター。「ホンマでっか!?TV」肥満治療評論家・漢方治療評論家。その他、テレビや雑誌で多数出演・監修。
※医師は広告とは関係しておらず、特定の商品の保証・購入を推薦するものではありません。
「難消化性デキストリン」という成分を知っていますか?
食物繊維の1種である難消化性デキストリンは、日本人の食生活が欧米化し、食物繊維の役割が重視されるようになったため、食物繊維の不足を補う目的で作られました。
難消化性デキストリンは、これまでに、整腸作用や食後の血糖および中性脂肪の上昇抑制作用、内臓脂肪の低減作用などの生理機能が注目され、多くの食品や飲料に使用されています。特定保健用食品の関与成分として、約3割を超える品目に配合されています。また、最近では、機能性表示食品にも利用されています。
そこで、今回は、難消化性デキストリンの基本的な情報とその効果、副作用などについてご説明したいと思います。
難消化性デキストリンとは?~基本情報~

まず、難消化性デキストリンの基本的な情報をご紹介したいと思います。
■難消化性デキストリンとはどんなもの?
「難消化性デキストリン」は、文字だけを見ても分かりますように、「消化されにくいデキストリン(デキストリンはデンプンの1種です。)」の総称です。
「難消化性デキストリン」は、トウモロコシのデンプンから作られます。原料のトウモロコシデンプンを培焼し(加熱してデンプンの構造を化学的に変化させ)、アミラーゼ(食物として摂取したデンプンを消化する酵素)により加水分解します。その中から得られた未分解物を調製した水溶性の食物繊維が、「難消化性デキストリン」です。
■さまざまな食品で利用
難消化性デキストリンは、水に溶けやすく、溶液はほぼ透明で、粘性が低く、異臭味がなく、甘味がわずか(砂糖の10分の1程度)です。このため、難消化性デキストリンは、食品に添加しても、その見た目や味を変えることがなく、加工性に優れています。
また、長時間、水溶液で保存しても濁りや沈殿が生じないという特徴を有しています。そして、酸性条件下でもほとんど変化がなく耐酸性に優れ、レトルト処理でも分解されることなく安定であることが確認されています。
さらに、他の食物繊維とは違って、ミネラルの吸収を阻害しません。
このような優れた加工性、安定性などから、現在では、飲料、菓子、ゼリー、スープなどのさまざまな食品に利用されています。
■脂肪や甘味料の代わりとしても利用可能
難消化性デキストリンは、脂肪に似たテクスチャー(歯ごたえ、歯ざわり、口あたりなど)を有するため、アイスクリーム、カレールウ、ソーセージなどにおいて、脂肪に代わる機能を持つ素材としての利用が可能です。しかも、この後ご説明するように、難消化性デキストリンは低カロリーであり、健康志向が高まっている現在では有望な成分といえるでしょう。
また、カロリーオフ、ノンカロリー飲料は、高甘味度の甘味料を用いることでカロリー低減を図っていますが、高甘味度甘味料は特有の後味があり、味切れが悪いことが問題になることがあります。これに対して、難消化性デキストリンを添加することにより、甘みの強さがピークに達する時間が早くなり、まろやかな甘味になるなど、優れた味の改善効果が得られます。
これらのことからも、難消化性デキストリンが優れた食品素材であることが分かります。
■さらにマスキング効果なども
難消化性デキストリンは、コラーゲンペプチドのような独特の風味のマスキングにも利用されています。
また、アルコール飲料では、難消化性デキストリンは、麦芽由来の酵素や酵母に利用されにくいという特徴がありますので、糖質ゼロのアルコール飲料などに利用可能です。低カロリーのビールなどは水っぽいものになることがしばしばありますが、醸造原料として難消化性デキストリンを使用すると、非発酵成分がもたらすコク味を加えることができます。さらに、二次的な効果として、ビールの泡をクリーミーにし、口当たりを向上させます。
■日本で発見・命名された難消化性デキストリン
難消化性デキストリンは、1988年(昭和63年)、食品用の加工デンプン、食物繊維などの製造・販売を行う松谷化学工業株式会社の研究者によって、発見され命名されました。
上でご説明しましたように、難消化性デキストリンは食物繊維の1種です。この食物繊維は、従来、栄養的に価値のないものと考えられてきました。しかし、さまざまな生理機能を有することが明らかになるにつれ、その役割が重視されるようになったことが、難消化性デキストリンの開発の背景にあります。
次の項では、難消化性デキストリンが属する「食物繊維」について、もう少し詳しくご説明しましょう。
■食物繊維とは?
難消化性デキストリンは食物繊維の1種ですが、「食物繊維」という名称を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。そもそも、「食物繊維」とはどのような成分なのでしょうか?
「食物繊維」とは、人間の消化酵素で消化されない食物中の難消化成分の総称です。食物繊維は、野菜や果物、海藻、キノコなどに多く含まれています。
食物繊維には多くの種類がありますが、大きくは、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」に分けられ、それぞれ、体に対する働きが異なっています。これらのうち、「水溶性食物繊維」には、ペクチン、コンニャクマンナン、アルギン酸ナトリウム、そして難消化性デキストリン、などがあります。
■食物繊維は「第6の栄養素」
食物繊維は、近年、研究が進み、糖尿病、ガン、心疾患などの生活習慣病の予防に効果があることが分かり、炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルの五大栄養素に続く「第6の栄養素」と呼ばれ、注目されるようになりました。
特に、精製された食品や脂肪・タンパク質の摂取量が多く、食物繊維の摂取量の少ないヨーロッパ、北アメリカなどの先進国では、心臓病、脳卒中、糖尿病などの非感染性の疾患が多いのに対し、高繊維食のアフリカ、アジアなどの開発途上国では少ない、というデータが疫学調査により明らかになっています。このことから、食物繊維の摂取がさらに重要視されてきています。
■不足している食物繊維摂取量
「第6の栄養素」と呼ばれている食物繊維には、摂取目標量が定められています。成人1日当たりの摂取目標量は、男性が19g以上、女性が17g以上とされています。
しかし、食の欧米化が指摘されている昨今では、穀物摂取量は顕著に減少しており、食物繊維摂取量は摂取目標量に達しておらず、若年層で特に少ないという特徴があります。
食物繊維の不足は、体の不調や病気につながりますので、健康維持や病気の予防のために、目標量を摂取することが重要です。
食物繊維は、普段の食事では目標量を取ることが難しく、不足しがちな栄養素としての認識が高まっています。最近では、食物繊維を配合したサプリメントや食品、飲料が数多く市販されていますので、これらをうまく利用するとよいでしょう。
■トクホの利用も認められている難消化性デキストリン
難消化性デキストリンは、トクホ(特定保健用食品)の有効成分として実績のある成分であるため、「規格基準型」のトクホの関与成分として認められています。
「規格基準型」のトクホとは、トクホのうち、これまでの許可件数が多く、既に科学的根拠が蓄積された指定成分が含まれている製品に許可されるものです。
規格基準型では、手続きの迅速化を図るために、消費者庁が定めている規格基準に則った申請を行うことで、消費者委員会の個別審査を受けることなく、消費者庁の事務局レベルの審査で許可されます。
難消化性デキストリンは、「おなかの調子を整えます」、「食後の血糖値が気になる方に適しています」、および「脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」という内容の表示で許可されています。
難消化性デキストリンはダイエットに効果的?

難消化性デキストリンは、約90~95%が小腸で消化されずに大腸まで到達し、その約半分がビフィズス菌などの腸内細菌の餌として利用され、残りは糞便とともに排せつされます。
腸内細菌により利用される際に短鎖脂肪酸(酢酸などの炭素数が6以下のもの)が生成され、これらは速やかに吸収され、エネルギー源となります。難消化性デキストリンの食物繊維部分のカロリーは、1グラム当たり1キロカロリー(1 kcal/g)です。
このことから、俗に、「ダイエットによい」などといわれることがあります。
肥満の予防に関する難消化性デキストリンの生理機能としては、これまでの研究から、脂肪の吸収スピードを遅延させる作用、内臓脂肪を低減する作用などが明らかにされています。
次の項では、これらの作用を含め、難消化性デキストリンの代表的な作用をご紹介したいと思います。
難消化性デキストリンの6つの効果

難消化性デキストリンは、特定保健用食品における豊富な利用実績や、専門家が読みその内容を審査した査読付き論文が多数存在することから、十分な科学的根拠を持った素材といえます。
この項では、難消化性デキストリンの持つ6つの優れた生理機能(効果)をご紹介します。
■1. 食後中性脂肪の上昇抑制作用
難消化性デキストリンには、食後中性脂肪の上昇を穏やかにする作用があります。
健康な成人(男女13名)に、脂肪を含む食事(ハンバーガーとフライドポテト)とともに、難消化性デキストリン5gを含む飲料を摂取させたところ、食後中性脂肪の上昇が抑制されたことが報告されています。
この研究報告から、難消化性デキストリンを脂肪の多い食事とともに摂取すると、食事に含まれる脂肪の吸収を遅らせ、食後の中性脂肪の上昇が抑えられることが分かりました。
■2. 内臓脂肪低減作用
内臓脂肪は、内臓の周囲に付いた脂肪をいい、お腹周りの肉が付いてくることで肥満が目に見えやすい症状としてあらわれます。そして、内臓脂肪が過剰に蓄積されると、内臓脂肪の脂肪細胞から、血糖値や血圧を上昇させたり、動脈硬化を促進させたりする物質がたくさん分泌されます。このため、内臓脂肪の蓄積は、生活習慣病のリスクを高めるのです。
BMI値が23以上の成人(男女38名)を対象として、難消化性デキストリンを10g含む茶飲料を1日3回、3か月間、食事とともに摂取させたところ、内臓脂肪の有意な低下が確認されました。また、この研究では、難消化性デキストリンの摂取により、ウエストが10 cm細くなった人がいたことも報告されています。
■3. 血清脂質の低下作用
血清脂質は、血液中に含まれる脂質です。中性脂肪、コレステロールなどがあり、そのバランスが崩れると、動脈硬化を促進します。悪玉のLDLコレステロールが多すぎると、これが血管壁にたまって動脈硬化を進めます。また、中性脂肪が多すぎても、善玉のHDLコレステロールが減ることなどによって、動脈硬化を促進する原因になります。
軽度肥満であり高脂血症の成人男性(12名)を対象として、10gの難消化性デキストリンを、食事とともに、1日3回、3か月間、摂取させたところ、中性脂肪と総コレステロールが低下したことが報告されています。
■4. 食後血糖の上昇抑制作用
食事から摂取した炭水化物(糖質)は、体内でブドウ糖に分解されます。この後、小腸で吸収されて、肝臓へ送られます。この小腸では、難消化性デキストリンがない場合、糖は速やかに吸収され、これによって、食後の血糖値が急激に上昇します。この状態が続くと、糖尿病などの生活習慣病の発症につながります。
一方、難消化性デキストリンがあると、その働きにより、糖の吸収スピードが緩やかになり、血糖値の上昇も緩やかになることが分かっています。
健常な成人(男女40名)を対象として、難消化性デキストリン5gを含む茶飲料を、食事(うどんと米飯)とともに摂取し、食後の血糖値を測定したところ、物理的作用による吸収遅延により食後の血糖値の上昇が抑えられることが分かりました。
■5. 整腸作用
難消化性デキストリンには、おなかの調子を整える整腸作用があることが分かっています。
一般的に、食物繊維は便秘を改善することが知られていますが、水溶性食物繊維である難消化性デキストリンも便秘を改善する作用を有しています。
健常な成人(27名)を対象として、難消化性デキストリン5gを含む飲料を10日間摂取させたところ、排便回数と糞便量が増加し、便の性状と排便後の感覚が良好になったという結果が得られました。
また、難消化性デキストリンは、腸内でビフィズス菌などの善玉菌を増やし、腸内菌叢(ちょうないきんそう)を改善し、下痢を改善できることも明らかになっています。
※難消化性デキストリンが機能性関与成分となっている「おなかの調子を整える」ことに役立つサプリメントです。
■6. ミネラル吸収促進作用
食物繊維はミネラルの吸収を阻害すると認識されてきましたが、低粘度で腸内細菌に利用されやすい難消化性デキストリンは、大腸でミネラルの吸収を促進することが明らかとされています。
女子大学生を対象とした試験では、難消化性デキストリンを食事とともに4週間摂取させると、摂取前に比べて、貧血の指標である赤血球ヘモグロビン、ヘマトクリット値が有意に増加することが確認されました。
また、男子学生を対象として、難消化性デキストリンを2週間摂取させ、カルシウム吸収への影響を評価したところ、カルシウム吸収の指標とされる尿中カルシウム排せつ量は、難消化性デキストリン摂取後は摂取前に比べて有意に増加しました。このことから、難消化性デキストリンの摂取によって、カルシウムの吸収が高まることが明らかになりました。
難消化性デキストリンの摂取目安量について
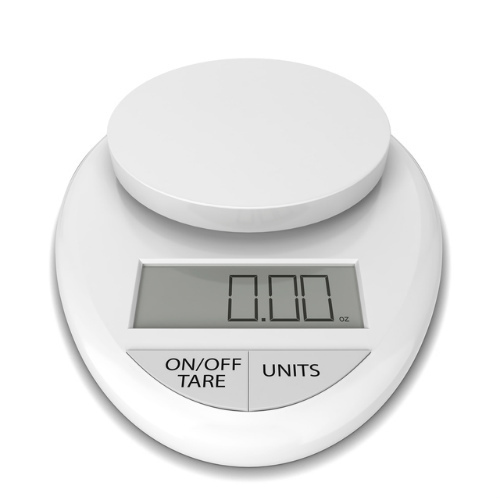
■日本の場合の摂取目安量
わが国では、難消化性デキストリンの1日摂取目安量は、「規格基準型」の特定保健用食品(トクホ)として表示できる分量が参考になると考えられます(消費者庁の「特定保健用食品(規格基準型)制度における規格基準」をご参照。URL: http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1569.pdf)。
具体的には、以下のとおりです。
・「難消化性デキストリン (関与成分) が含まれているのでおなかの調子を整えます」の表示では、3~8g。
・「食物繊維 (難消化性デキストリン) の働きにより、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています」の表示では、4~6g。
・「食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる食物繊維 (難消化性デキストリン) の働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」の表示では、5g。
■アメリカの場合の摂取目安量
アメリカでは、難消化性デキストリンは、FDA(アメリカ食品医薬品局)によって、1990年(平成2年)、GRAS(一般に安全と認められる食品)の認定を受け、1日の摂取量の上限を明確に定める必要がないほど、安全な食品素材であると認められています。
なお、難消化性デキストリンは、発売後25年以上経過し、世界中で使用されており、FDAが目安としている「広範囲に最低25年」という条件を満たしていることから、十分な食経験があり、安心して使用できる素材といえます。
難消化性デキストリンのおすすめの飲み方・摂取方法

■食事に含まれる脂肪が気になるなら、1日1回食事とともに5g
先ほど、「規格基準型」の特定保健用食品として表示できる難消化性デキストリンの1日摂取目安量について、「食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させる食物繊維 (難消化性デキストリン) の働きにより、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」の表示では、5gとご紹介しました。
この「5g」という量については、消費者庁の基準では、「1日1回食事とともに摂取する目安量」という注釈が付いています。
したがいまして、ダイエットをされている方や、ダイエットに興味のある方は、1日1回食事とともに5g程度取るのがよいでしょう。
また、摂取を継続する場合、その期間につきましては、この後ご紹介しますように、15g程度で4週間摂取しても問題がなかったことから、まずは、4週間程度摂取し続けてみて、効果があらわれるかどうか確認するのがよいでしょう。
■食後の血糖値が気になるなら、1日1回食事とともに4~6g
こちらも、食事の脂肪が気になる場合の摂取と同様に、「4~6g」という量は、「1日1回食事とともに摂取する目安量」です。普段の食生活などから血糖値を気にしている方は、1日1回食事とともに4~6gを目標に取るのがよいでしょう。
ただし、血糖値に異常を指摘された方や、糖尿病の治療を受けておられる方は、事前に医師などの専門家に相談のうえ、摂取されることが肝要です。
■おなかの調子を整えたいという方は、1日3~8g
最後に、「おなかの調子を整えたい」という方の難消化性デキストリンの1日摂取目安量ですが、これは3~8gになります。
また、摂取を継続する場合、その期間につきましては、先にご紹介しましたように、難消化性デキストリン5gを含む飲料を10日間摂取すると、排便回数と糞便量が増加したという報告があることから、まずは、10日間程度摂取し続けてみて、様子をみるのがよいでしょう。
なお、後述しますように、過剰に摂取すると、おなかがゆるくなることがありますので、注意が必要です。
難消化性デキストリンの副作用と危険性

■副作用と健康被害について
難消化性デキストリンを15g程度で4週間摂取させた試験では、特に問題となる症状は認められていません。
また、難消化性デキストリンを1日3回毎食前に、10gを16週間にわたって摂取させたところ、血圧などの生理学的検査値には異常が認められませんでした。
そして、下痢誘発の最大無作用量(生涯摂取しても何も影響が出ないと判断される最大の量)は、男性で1.0 g/kg体重以上、女性では1.1 g/kg体重以上と報告されています。
以上のように、難消化性デキストリンは、他の難消化性糖質と比べ、下痢発症のリスクが低く、さまざまな試験により十分安全性が確認された成分といえます。
■過剰摂取した場合について
難消化性デキストリンは、過剰摂取または体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。また、多量摂取することによって、病気が治癒したり、健康がさらに増進したりするものではありません。
通常の食品として摂取する条件ではおそらく安全と思われます。しかし、難消化性デキストリンを含む食品は数多く流通しているため、複数の製品から、気づかないうちに過剰量を摂取する可能性があることに注意する必要があります。このため、他の食品からの摂取量を考慮し、適量を摂取することが大事です。
したがいまして、健常者であれば、過剰摂取しない限り、摂取することによるデメリットは少ないと考えられます。
なお、妊婦・授乳婦および小児では、サプリメントなど濃縮物として摂取する場合の安全性に関して、信頼できる十分な情報が得られていません。このため、妊婦などが摂取する場合には、注意が必要と考えられます。
■遺伝子組換え原料について
難消化性デキストリンは、トウモロコシを原料として作られ、遺伝子組換え原料や作物に対する懸念を抱く方もいることでしょう。
日本では、非遺伝子組換え製品へのニーズは根強いものがあります。さらに、遺伝子組換え先進国のアメリカでも、最近、大手食品メーカーが主力商品に使用するコーンスターチをすべて非遺伝子組換えトウモロコシを原料にしたものに変更し、「遺伝子組換え原料は不使用」と表示することを発表しました。
遺伝子組換え食品に関しては、特にインターネット上において、情報が極端な内容であったり、正確性を欠いていたりするものがみられます。正確な情報を得ていないのに過剰に反応している、という場合もあります。
商品説明に遺伝子組換え原料を使用していない旨が示されている商品も販売されています。気になる方は、このような商品を利用されるとよいでしょう。または、メーカーに直接確認してみるのもよいかもしれません。
難消化性デキストリンを含む食品やサプリ3つ
■①食事と一緒に十六茶W(ダブル)
アサヒ飲料のトクホで認可を受けているお茶です。
商品説明には以下のように効果が出ています。
「本品は食物繊維(難消化性デキストリン)のはたらきにより、食後の糖の吸収と食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、食後の血糖値が気になる方や血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。」
カロリーが気になる人は、食事のときに一緒に飲んでみましょう。
■②難消化性デキストリンの粉末
難消化性デキストリンを含む食品やサプリメントはたくさんありますが、自分で難消化性デキストリンそのものを手に入れて、食事や飲み物に含めて摂取することもできます。
■③おなか快調宣言
「おなかの調子を整える」効果のあるサプリメントで、累計2,000万本以上売れています。
楽天ランキング第1位の販売実績、 全国のテレビCM放送、モンドセレクション受賞、と輝かしい商品実績を誇っています。
おなかの調子が悪いな…と感じていたら、試してみてください。
※商品の詳細は、以下のバナーをクリックしてください。
まとめ
「難消化性デキストリン」は、優れた生理機能、加工性、安定性などから、わが国だけでなく、世界中で利用されています。
また、難消化性デキストリンは、「食物繊維」の1種です。食物繊維は、昔は、食物中の「カス」として扱われ、栄養学的に価値のないものと考えられていましたが、近年、さまざまな生理機能を持つことが明らかになっています。現在では、「第6の栄養素」としてその重要性が認識され、日本人の食事摂取基準においても目標量が設定されており、不足しがちな栄養素としての認識が高まっています。
難消化性デキストリンについていえば、科学的根拠が豊富で優れた生理機能が認められています。さらに、最近では、「ダイエットによい」といわれ、世の女性たちの注目を浴びています。
これまでの研究では、難消化性デキストリンを摂取することによる、脂肪の吸収スピードを遅延させる作用、内臓脂肪を低減する作用などが明らかにされています。
難消化性デキストリンを含む食品や飲料は、数多く市販されています。このような食品などを利用すれば、難消化性デキストリンを効率的に摂取することができます。
しかしながら、優れた効果があるからといって、多量に摂取するのはよくありません。これは、先にご紹介したとおりです。
過度なダイエットは逆効果であり禁物です。日頃から、バランスのとれた食事、適度な運動などを心がけるようにしたいものです。













![さつまいもの栄養成分・効果効能5つとおすすめの食べ方6つ[専門家解説]](/media/uploads/article/image/203/thumb_lg__________1.jpg)

